市川先生と最初にお会いしたのがいつどこでなのかの記憶をどうしても呼び起こすことができないのですが、岩崎研究会であることは確かで、いつかの夏の旅行なのではないか—と思っています。そしてその後、中央大学で学部は異なれど、ご一緒する機会に恵まれました。それですっかり市川先生のことは「辞書 x ジョンソン研究者」としてインプットされていたので、お若い頃は生成文法を精力的に研究されていたというのが驚きでした。また、勉強の機会を得るために様々な場所に積極的に足を運び、人との交流も楽しむ先生の学びの歴史を知ることができました。
私は研究社の『新英和中辞典』第5版で育った — 高校の3年間、そして大学でも愛用していました — ので、いつか英和中に関わることができたら、と思ってきましたが、まずは編者のお一人である先生のお話を聞くことができてとても嬉しかったです。また、先生は私の好きな『新編英和活用大辞典』のお仕事もされており、羨ましく思うのと同時に、初心を思い出すことができたように思います。職場の大先輩である先生の、研究を教育に反映させそれをまた研究に、というおことばも反芻していこうと思います。
市川泰男
Yasuo ICHIKAWA- 1947年
埼玉県生まれ
- 1969年
埼玉大学教育学部(英語専攻)卒業
- 1972年
東京外国語大学大学院ゲルマン系言語専攻(英語学)修士課程 修了
- 1972年
玉川大学文学部外国語学科 助手(73年 講師)
- 1979年
中央大学経済学部 専任講師(81年 助教授、90年 教授)
- 2017年
中央大学経済学部定年退職(名誉教授)
『研究社英和中辞典』、『ライトハウス英和辞典』など数多くの英和辞典の編集、執筆に携わる。
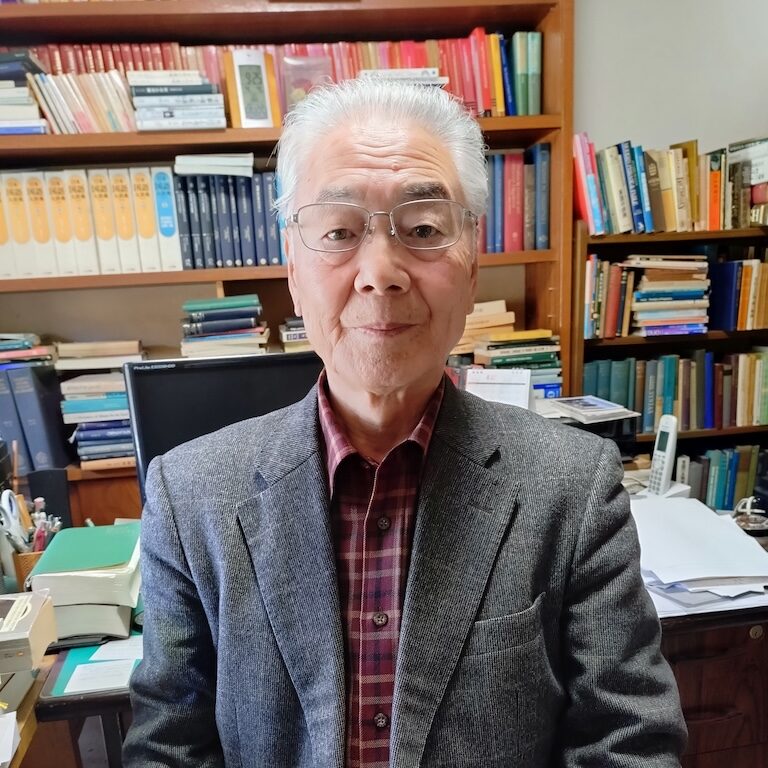
『研究社英和中辞典』、『ライトハウス英和辞典』など数多くの英和辞典の編集、執筆に携わる。
- 1947
埼玉県生まれ
- 1969
埼玉大学教育学部(英語専攻)卒業
- 1972
東京外国語大学大学院ゲルマン系言語専攻(英語学)修士課程 修了
- 1972
玉川大学文学部外国語学科 助手(73年 講師)
- 1979
中央大学経済学部 専任講師(81年 助教授、90年 教授)
- 2017
中央大学経済学部定年退職(名誉教授)
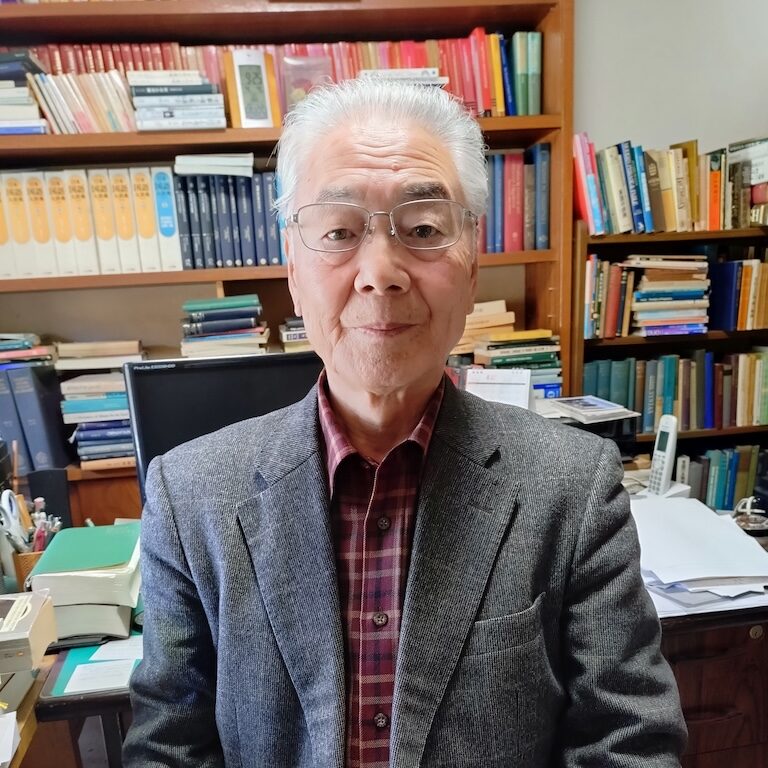
Interview
インタビュー2025.03.31 実施
-
01.-
辞書編纂者になるまで
-
英語の勉強はいつ始められましたか。

-
中学校です。秩父の影森中学校に通っていました。英語は何人かの先生に教わりましたが、一人とても発音のきれいな菅原先生という方がいました。先生は、秩父の教会へ行って、そこで英語でコミュニケーションを取っていたようです。3年生の時には、小嶋登先生という、後に校長先生になって、当時荒れていた学校を立て直すために「旅立ちの日に」という卒業式でよく歌われる合唱曲の歌詞を書いた方が、担任の先生であり、英語も教わりました。have to の発音を説明された時に、有声音、無声音、に意識が行くようになったことも覚えています。小嶋先生とは、先輩からの声掛けで大人になってからゴルフでご一緒する機会があって、どちらかというとフェミニンな感じの先生がミスをした時に「ちくしょう!」と口にされて、小嶋先生でもそんな言葉を使うんだ、と思ったことがありました。が、素晴らしい先生とのご縁をとても誇りに思っています。
学校の授業のほかに、当時埼玉大学の学生だった宮城先生—後に地元の中学校の英語教師になりました— に6〜7人で英語を教わっていました。一番仲の良かった友人の家が教育熱心で、彼の家に集まっていました。学校の勉強のおさらいですよね。今でも覚えているのは、1年生の時に、suburb(郊外)という単語を、学校の先生は第二音節にストレスを置いて発音していたのでそう覚えていたら、それは間違いで第一音節に置いて発音するんだと。二人の先生の発音が異なるので、どちらが正しいのか混乱しちゃって、中学校の英語教育ではきちんとした発音を教えることが大事だと感じました。
-
中学校の時に辞書は使っていましたか。

-
中学生の時に辞書を使った記憶はないですね。教科書の巻末にある単語リストを使って、上級生が英語から日本語、日本語から英語にする単語テストをしてくれて、合格をするとスタンプを押してもらったりしました。
-
英語は得意で楽しんで勉強されていたのですね。

-
数学と英語が大好きでした。英語は、先生に勧められて、弁論大会のようなものに出場したこともありましたね。優勝したわけでもなく、作文を書いて他の学校の先生もいるところで発表しただけでしたけど。
-
高校ではどのように英語を勉強していたのですか。

-
中学校では、テニスばかりやっていたので、高校でもテニスを続けようと思っていたのですが、進学を考えているなら文化部の方がいいよと言われて、ESSに入りました。英語劇もしましたね。オー・ヘンリーの「最後の一葉(The Last Leaf)」で、市川は医者の役をやれ、と言われてやったんですが、セリフが ‘There you are.’ しかないんだよね(笑)。自分の出番が終わってほっとしてると、最後の一葉が描かれた窓のセットが外れて大騒ぎになったりしていました(笑)。青春の思い出ですね。
生徒会の仕事をした時には、加須市にある不動丘高校との交歓会があって、バス10台くらいで生徒がやってくるなかなか大がかりなものだったんですが、不動丘高校のESSと図書室で一緒にディスカッションをするような企画を行いました。
埼玉大学の教育学部出身の先生が多かったのですが、シェイクスピアの「弱き者よ、汝の名は女なり」とか「ブルータス、お前もか」などの台詞を、断片的にですけど、教えてくれたことはよく覚えてますね。友達の通訳者を連れてきて話をしてくれた先生もいました。東大出の先生もいましたが、ただ暗記させるだけで授業はちっとも面白くなかったですね(笑)。辞書は、学校指定の『クラウン英和辞典』を使っていました。
-
大学で英語を専攻しようと思ったのは自然な流れだったのでしょうか。

-
高校3年生の夏に、都内の予備校の夏期講習に通ったんですが、英語は成績が貼り出されるのに、数学は貼り出されない。数学よりも英語の成績がよかったこともあって、英語を専攻することにしたのかもしれません。漠然と教師になろうかな、文部省に行こうかな、と考えていたのですが、年の離れた兄に、文部省を目指すなら東京大学に行かないとダメだよ、なんて言われてね。
受験の年は、埼玉大学の文理学部がなくなって教養学部ができた年だったんですよね。教育学部よりも「教養」学部のほうがかっこいいと思っていたので、教養学部に行きたかったんだけど、システムがよく分からなかったし、先に教育学部の試験に合格したので、その後の教養学部の試験は受験せず結局教育学部に進学することにしました。
-
埼玉大学の教育学部ではどのような勉強をされたのですか。

-
まず英語専攻の主任教授であった黒河内豊先生には英語教育全般について教えて頂きました。『斎藤秀三郎伝』の著者、大村喜吉先生の授業では、市川三喜の『聖書の英語』を、和田善太郎先生の授業では、A. S. ホーンビーの Guide to Patterns and Usage in English (1953) やザントフォールト(R. W. Zandvoort)の A Handbook of English Grammar を読みました。大学で初めて外国人教師に習いましたね。家内は同級生なんですけど、高校生の時に牧師さんに英語を習っていて発音がけっこう上手で、子どもたちに「家で一番発音が悪いのはお父さんだよね」と言われるのですが「でも語彙なんかはすごいよね」と褒めてもくれます(笑)。
埼玉大学教育学部の英語専攻は — 私の学年は13名でしたが — 一学年10〜15名程度だったので、同じ授業に異なる学年の学生がいて、優秀な先輩を身近に見ながら学べたのはとてもよかったですね。辞書は『岩波英和辞典』を使っていました。
大学でもESSに入りました。新入生の歓迎祭で英語ドラマを演じていた先輩たちがかっこよくてね。Conversation, Debate, Drama などのセクションがあったのですが、3年生の時には岡村祐輔さんの後をついで Conversation のチーフになりました。お昼休みに、日本人学生同士で「チャット」と言って英語で会話の練習をしていました。みんな「英語を話したい」「ネイティヴと英語で話したい」という気持ちが強くあったので、アンケートを作成して、日比谷公園や皇居へ出かけて行って、外国人観光客をつかまえてインタビューをして、その結果を大学祭で発表するなどしていました。どうにかして英語を話したい、という時代ですよね。
-
卒業論文ではどのようなテーマを扱ったのですか。

-
文法が好きで、イェスペルセン(Otto Jespersen)の Essentials of English Grammar や Analytic Syntax など、色々と読んでいました。ローゼンボウム(Peter S. Rosenbaum)の The Grammar of English Predicate Complement Constructions (1967) を読んで変形文法の新しい風を感じ、イェスペルセンの ‘nexus’ の概念との類似性から、‘The studies of theories on Nexus’ という卒論を書きました。 卒論の口頭試問では、意味論についても質問をされて、「その程度の理解では本を読んだというよりも本を見たというに等しい」と言われたことをよく覚えています。
-
大学院へ進学しようと思ったのはどうしてですか。

-
1学年上の岡村祐輔さん(熊谷高校卒・後に山梨大学教授)や2学年上の島村宣男さん(浦和高校卒・後に関東学院大学教授)といった先輩が、出来たばかりの東京外国語大学の大学院に進学していたので、私も進学を考えるようになりました。4年生の時は、前期に埼玉大学教育学部附属中学校に教育実習に行って、後期は卒論執筆をしながら、大学院の試験勉強をしていました。『英文法辞典』(大塚高信編、三省堂)と『英語学辞典』(市川三喜編、研究社)をずっと読んでいましたね。ですので、授業で「この we の用法は?」と聞かれたりすると ‘royal we’ であるとか ‘editorial we’ であるとか、すぐに答えられるようになりました。
-
東京外国語大学大学院での学びについて教えてください。

-
まずはレベルの違いに驚きました。梶木隆一先生(故・東京外国語大学名誉教授)の授業では、ヘンリー・ジェイムズの The Wings of the Dove を読んだのですが、当時の英語力では歯が立たず、一緒に受講していた塩川さんという日比谷高校で英語は1番、2番だったという先輩に喫茶店で教えてもらったことをよく覚えています。半田一郎先生(故・東京外国語大学名誉教授)の授業では、ロビンス(R. H. Robins)の General Linguistics を読みました。小浪充先生(故・東京外国語大学名誉教授) — この先生は英語ができると言われていて — の授業では S. I. Hayakawa の Language in Thought and Action を読みましたが、後々とても役に立ちました。また、必修の言語学の授業だったかと思うのですが、金田一春彦先生(故・東京外国語大学名誉教授)が黒板の前を、右に左に歩きながら講義をされるのですが、時折前の方にチェコ語の千野栄一先生が座っていて、金田一先生と、学生は蚊帳の外で(笑)、議論を始めたりして大学院とはこういう場所なんだといたく感心しました。日本語のリズムの話をされた時に「この土手に登るべからず警視庁」というのを聞いて、確かに五七五だな、と面白く感じたことをよく覚えています。この授業のレポート課題は、英語学、英文法に関する論文を選んで訳出するというもので、私は随分と時間をかけて command という概念に関する論文を訳して提出しました。
-
指導教授は松田徳一郎先生だったのでしょうか。

-
名目上は梶木先生が指導教官だったのですが、文法に興味があったので、松田徳一郎先生(故・東京外国語大学名誉教授)の指導を受けられないかと思って梶木先生に相談したところ、先生は嫌な顔ひとつせずに快く了承してくださったので、松田先生に実質の指導をしていただくことになりました。松田先生はアメリカから帰国されて、新進気鋭の言語学者として生成文法を教えられていました。学部では Aspects (of the theory of syntax) の講義をされていましたので聴講しました。大学院では、ユリエル・ワインライク(Uriel Weinreich)の Language in Contact を読みました。 また、先生と一対一で一冊の本を読んだことが何よりの思い出です。アンダーソン(John M. Anderson)の The Grammar of Case を私が訳をしていき、理解できないところを先生が解説してくださるという形式で贅沢な時間でした。フィルモア(C. Filmore)の ‘The case for case’ (1968) の論文に影響を受けて、修論は、‘Case relations and prepositions in English’ という表題で書きました。
-
大学院では辞書のお仕事はされなかったのでしょうか。

-
梶木先生に紹介されて、『小学館ランダムハウス英和大辞典』(1973)用例収集のアルバイトをしました。これが辞書編纂に関わった最初の仕事ということになるかもしれません。ただ、用例を集めているときに、辞書を作っているという意識はなかったですね。第4巻の巻末に「協力者名簿」があり、私の名前も掲載されています。
-
-
02.-
岩崎研究会と研究社の辞書の仕事
-
岩崎研究会に入会されたのはいつですか。

-
大学院の後半だったかな、津谷武德さん(故・國學院大学教授)に誘われて竹林滋先生の研究室に行って、それから入会したように記憶しています。
大学院を終えてからは府中にいたので、研究会が八丁堀あたりで開かれていた頃は例会にも出席していたのですが、長女が生まれて秩父に引っ越してから読書会からは足が少し遠のいてしまいました。
-
竹林滋先生とは研究会に入ってからのお付き合いだったのでしょうか。

-
そうです。竹林先生の音声学の講義は受けていないんですよ。一番後悔していることです。当時、私の頭は文法のことでいっぱいで、音声学にはあまり関心がなかったんですよね。
岩研の夏の旅行は、教授、助教授、講師、大学院生で料金設定が違っていて、竹林先生のそういうところは素晴らしいと思っていました。旅行中に先生方から色々な話を伺って、非常にためになりましたね。小室さんがこのサイトで「印税で家が建てられる」時代と書いているけれど、私は竹林先生が「給料は全部税金で持っていかれる」とおっしゃっていたのを覚えています(笑)。辞書の執筆に関しては、執筆内容と期限遵守、両方ともAがいいが、A-B / B-A までは許されるとおっしゃっていました。私は期限は守っていたから、B-A は達成できたかな、と思っています。
-
岩崎研究会に入られて研究社の辞書の仕事をするようになったのでしょうか。

-
そうですね。最初は、執筆のために OALD や LDOCE を参照する作業をしたような記憶があります。『ライトハウス英和辞典』や『ルミナス英和辞典』などの仕事をさせてもらいました。学習英和辞典としては、『ルミナス英和辞典』でかなり完成度は高まっているのではないかと私は見ています。
私の娘はロンドンで仕事をしているのですが、勤めている会社の社長がノーフォークの方にライトハウス、灯台を所有していて、そこに泊まりに行かせてもらった時に、『ライトハウス英和辞典』を一冊献呈してきました。
-
辞書分析もかなりなさったと思いますが、どのようなことが印象に残っていますか。

-
辞書分析グループに初めて加えていただいたのは Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition の分析 (1) (Lexicon no. 18 )で、当時はまだ日本語で書いていました。私はセクション IV の用例を担当したのですが、初めてでしたので先輩の桜井雅人さん(故・一橋大学名誉教授)に分析方法をお聞きした記憶があります。それに、中尾啓介先生(電気通信大学名誉教授)などが執筆されている初版の分析と比べて遜色がないものにしたいという気持ちはありましたね。OALD の5版(Lexicon no. 26 )、LDOCE の4版(Lexicon no. 35)も分析しました。LDOCE 4版の時には、執筆者全員が蓼科の清水あつ子さん(明治大学名誉教授)の別荘にお邪魔して分担などを話し合ったりしました。20年も前の楽しかった思い出です。小室さんとも Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms (2008) の分析(Lexicon no. 41)をしましたね。授業でもこの辞書に基づいて類義語の話をしたことがありますよ。また、久しぶりに昔の辞書分析を少し覗いてみましたが、教室で英語を教える際に参考になるような情報や辞書を執筆する上で心得ておくべき事柄などが満載ですね。岩研の先輩たちの言葉・英語に対する飽くなき探究心、あるいはよりよい辞書を作りたいという情熱を強く感じましたよ。
-
-1
Ichikawa, Y., T. Kanazashi, H. Saito, T. Kokawa & K. Dohi. 1996. An Analysis of Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Fifth Edition. Lexicon 26, pp. 142-177.
https://globalex.link/wp-content/uploads/2019/08/Lexicon-26_004.pdf
-
-2
Ichikawa, Y. , A. Shimizu, R. Takahashi, T. Kanazashi & Y. Ishii. 2005. An Analysis of Longman Dictionary of Contemporary English, Fourth Edition. Lexicon 35, pp. 1-126.
https://globalex.link/wp-content/uploads/2019/08/Lexicon-35_001.pdf -
-3
Komuro, Y. & Y. Ichikawa. 2011. An Analysis of the Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms. Lexicon 41, pp. 11-59.
https://globalex.link/wp-content/uploads/2019/08/Lexicon-41_002.pdf
-
-1
-
市川先生は『新編英和活用大辞典』(1995)の「執筆協力」にもお名前がありますよね。

-
1993年の終わり頃から95年4月の完成までの間、執筆に関わりました。ちょうど英和中辞典の作業がひと段落ついた頃、日本人執筆者が足りないということで、編集部の逸見さんから連絡がありました。編集部が見出し語リストを作成し、コーパスから用例を抽出して、要不要を判別する。記述するものについてはどこに記載するかを決める。そして、そのデータを元に執筆をする。私はプロジェクトの最後の方に参加したので校正的な仕事だったかと思います。次から次へとゲラがきてチェックをしていた記憶があります。violent patient が「暴力的な患者」などとなっていて、コンテクストを考えれば「暴れる患者」という方がしっくりくるかな、というようなことをゲラに書き込んでいましたね。‘in connection with’ という表現は、犯罪に関するニュースでいつも出てくるんですが、当時の一般の学習英和辞典では、そういった例文までは拾っていないところ、『活用大辞典』では取り上げられていて、さすがだな、と思ったことがあります。
-
-
03.-
玉川大学・中央大学における研究生活
-
玉川大学に助手として着任された頃のことを教えてください。

-
1972年に玉川大学の文学部に外国語学科が設立されて、大学院でお世話になったアメリカ文学がご専門の西田実先生(故・東京外国語大学教授)が玉川大学の岩垣守彦先生に私を推薦してくださり、助手として採用されました。そして翌年9月に講師になりました。
とても良い大学でしたね。英文科に大学院ができて、松村達雄先生(故・東京大学名誉教授)はローレンス・スターンの『センチメンタル・ジャーニー』の訳者ですが、それを読んでいました。私も本を買って自分なりに読んで、イギリス文学とはこういうものか、と思った記憶があります。大佛次郎賞を受賞した富士川英郎先生(故・東京大学名誉教授)のドイツ文学の授業には、院生の履修者がいなかったので、助手の私が一人だけで授業を受けていたりしました。巻末の注を参考にして訳をしたら、その注は間違っていますね、と先生が出版社に電話をしたりしたこともありました。
言語学では、田中春美先生(南山大学名誉教授)がいらして、フィルモアの論文集を翻訳をされていました。‘Toward a modern theory of case’ と ‘The grammar of hitting and braking’ を頼まれて訳しました。『格文法の原理:言語の意味と構造』(1975)に、協力者として名前を載せてくれたんだけど、名前が間違っていたのでちょっとがっかりしました。
アメリカ文学の岡鈴雄先生は、ヘンリー・ジェイムズの専門家だったのですが、読書会を開いていて、ヘンリー・ジェイムズの作品を読んでいるというので、お願いして入れてもらいました。月に一回、当時、同僚だった山崎真稔さんと何人かで先生のご自宅にお邪魔して、作品を読んで訳していたのですが、大学院の時、梶木先生の授業ではよくわからなかったヘンリー・ジェイムズがいくらか理解できるようになった気がしましたね。
-
ご研究としてはやはり文法が中心にあったのでしょうか。

-
7年くらい玉川にいたわけですが、その時も文法を主に研究していました。助手の時に、東京言語研究所で講座をいくつか受けていたのですが、プリンストン大学から帰ってきた梶田優先生(上智大学名誉教授)がチョムスキーの Syntactic Structures (1957) を一緒に読んでくれたんです。その時に、 ‘grammatical’ の ‘t’ の発音を指摘されたんですよね。鮮明に覚えています。助手だった私に、アメリカ英語では「ラ行」の音のように発音されることを教えてくれたんですよね。辞書でこの t の音が記述されるまでにはかなり時間がかかったように思います。他にも、国広哲弥先生(故・東京大学名誉教授)の意味論や、鈴木孝夫先生(故・慶應義塾大学名誉教授)の社会言語学の講座も取りました。国広先生の講座では、「触わる」と「触れる」の違いについてレポートを書きました。
1975年の夏に、はじめてロンドン大学のサマー・スクールに参加しました。音韻論の授業だったのか、発音の授業だったのか忘れてしまったのですが、先生が good にストレスを置いて ‘Good morning.’ と言って授業を終えるんですよね。 「おはよう」ではなく「さようなら」の意味になる。こういう用法を記述している辞書もあるけれども、そういったことを実際に経験できてよかったです。
ジェフリー・リーチ先生(Geoffrey Leech)の講演を聞いた時には、持参していたインディアペーパーの POD にサインをもらったりもしました。with best wishes と書いてくれました。あの頃は、みんな Meaning and the English Verb (1971) を読んでいましたから。
強意語の badly について調べていた時は、Time や Newsweek などから用例収集をしてカードを作っていました。これには相当時間がかかっていたんだけど、今だったらコーパスがあるから一発で調べられますね。松田先生には、雑誌を二部買って片方を切り抜き用にすれば間違いがない、と言われましたが、二冊買うような余裕がなかったから手書きで作成していました。
-
-4
東京言語研究所
https://www.tokyo-gengo.gr.jp/
-
-4
-
どのような経緯で中央大学経済学部に移られたのですか。

-
秩父に引っ越したら玉川大学に通うことが大変になってしまったので、岩崎研究会の読書会の後で、東信行先生(故・東京外国語大学名誉教授)と津谷さんと3人で食事をした時に、相談したんです。そうしたら、その年の夏に、竹林先生からお電話をいただいて「中央大学の話がある。八高線を使えば通える」と。それで中央大学に職を得ました。
-
中央大学での研究生活はどのようなものでしたか。

-
中央大学の経済学部に定年退職まで在職しましたが、自由に研究ができる素晴らしい環境でした。特に大学に感謝していることは1991年4月から(研究期間を1年延長してもらって)1993年3月までの2年間の在外研究と2001年の特別研究です。在外研究は、松田先生にインディアナ大学で同僚であったマシューズ(P.H. Matthews)先生を紹介していただきケンブリッジ大学の言語学科においてもらいました。マシューズ先生の Morphology や Syntax は読んでいましたから嬉しかったです。当時、ケンブリッジには意味論のジョン・ライアンズ(John Lyons)もいましたね。いくつかの講義を聴講させてもらいましたが、ケンブリッジでの生活そのものが勉強になりました。テレビ、ラジオでできるだけ英語に接していました。新聞は The Mirror を配達してもらって、ためになる表現などをパソコンに打ち込んでいましたね。辞書は BBC English Dictionary (1992) を読んでいた形跡が残っています。とてもラッキーだったことに、ケンブリッジで借りた家(バンガロー)の家主は何と Christ’s College のマスターであったハンス・コーンバーグ(Sir Hans Kornberg)という有名な生化学者でした。 マシューズ先生は St John’s College に属しておりました。それぞれのコレッジのディナーに招待されたのでそのお礼に我が家での夕食にお招きしたら、別々の機会でしたが、お二人とも来てくれました。ケンブリッジでの生活ではコレッジに属することが重要であることに気付き2年目には(大学院レベルの)Darwin College に入れてもらいました。ケンブリッジでのことを話すときりがないので止めますが、この2年間は私と家族にとって人生で最も幸せな期間だったと思います。
2001年の特別研究期間には5月ごろから半年間ロンドンで生活しました。この年には諏訪部仁さん(故・中央大学名誉教授)が在外研究でロンドンにいらしたので時々お邪魔したり、私の運転でS.ジョンソンの生誕地リッチフィールドを訪れたりもしました。この二つの研究期間に研究したことはその後に執筆した論文に活かされていますが、とにかく英国でのもろもろの経験が授業で活かされたことは間違いありませんね。
-
市川先生は『エコノミストとビジネスウィークを読む辞典』(2002)なども編纂されていますが、これは経済学部で教えていらしたからでしょうか。

-
1981年に、文部省の「英語教育担当教員の連合王国派遣」という制度に応募して、英国レディング大学に行きました。そこで、authentic English ということがさかんに言われていました。英語教授用に編集されたものではなく「生の英語」を使いなさい、と。それで経済学部の学生と The Economist や BusinessWeek を読んだり、BBC News を教材として使うようになりました。BBCのニュースをDVDに録画しておいて、授業で扱うのに適したものを選び、それを書き起こして、同僚だったマサレラ先生(Peter Derek Massarella)(中央大学名誉教授)にお願いしてチェックしてもらって、聞き取り教材を作っていました。マサレラ先生はただの一度も嫌な顔をされたことがなくて本当に感謝しています。田崎研三先生(中央大学名誉教授)という、私より一回りくらい上の先生が、やはり The Economist などをよく読まれていて、そういった教育活動から、『エコノミストとビジネスウィークを読む辞典』(2002)、『レキシコン : The Economist と BusinessWeekを読む辞典』(2008)が生まれました。もう一人の著者である松谷泰樹さんは田崎先生の教え子で、経済の専門家です。英語がよくできる人なので、英語の例文をまず私が日本語にして、田崎さんと松谷さんが経済のことばに翻訳していました。
-
中央大学在職中には、ジョンソン研究も行っていらっしゃいますよね。

-
1999年4月に中央大学人文科学研究所「S.ジョンソン研究」グループは誕生しました。諏訪部仁さんに声をかけ、ジョンソニアンの仲間であった江藤秀一さん(当時筑波大学教授)、芝垣茂さん(故・東海大学教授)と4人の小さな研究会を作りました。ジョンソンの『英語辞典』の企画書やその序文(Preface)を読んでいました。その頃、人文科学研究所で翻訳叢書を出すことになったので、手を挙げて最初に翻訳をした『スコットランド西方諸島の旅』(2006)は、中央大学人文科学研究所翻訳叢書の第一号でした。その後、『ヘブリディーズ諸島旅日記』(2010)を翻訳した後に一度活動を停止しましたが、ジョンソンの旅行記でまだ翻訳されていないものを翻訳しようと話がまとまり、活動を再会し、『ジョンソン博士とスレイル夫人の旅日記 : ウェールズ(1774年)とフランス(1775年)』(2017)を出しました。
-
-
04.-
『研究社新英和中辞典』の編集と執筆
-
『新英和中辞典』のお仕事について教えてください。

-
どうして編集委員になったのかは定かではないのですが、想像するに『ライトハウス英和辞典』などの仕事を評価してもらったのか、第5版から吉川道夫先生(故・元中央大学教授)が編者として加わったこともあったのか、編集会議に最初から出席していたと思います。後で知ったのですが、編集部の岡田譲介さんは埼玉大学の先輩で、執筆にお名前のある利根川浩一さんは岡田さんの同級生だそうです。
吉川先生は、意味の流れを意識して原稿を執筆しなさい、といつもおっしゃっていましたね。ですので、その点をとにかく気をつけて執筆していました。4版から5版の改訂では、小稲義男先生(故・上智大学名誉教授)と吉川先生が中心となって、編集方針において大きく舵をきったと思うんですよね。5版のまえがきに「文型の表示は初版以来の一大特徴であったが、今回は使用者の便を考慮して、各文型と語義・用例の有機的対応をはかり、いっそうわかりやすく使いやすいものとした」とあります。たとえば、動詞の見出し語では、文型ごとに a. b. などと語義をわけて、訳しやすいようにそれぞれに語義を与えています。ある時、小島義郎先生(故・早稲田大学名誉教授)に、これは語義ではないのではないかと、言われたことがあります。これは本当に難しい問題で、文型に合わせた訳があることで、学習者は情報の整理はつくけれども、学習者から自由な発想で勉強することを奪うかもしれない。情報を与えすぎることの功罪ですね。英語を学ぶ人にとってはどっちが学びやすいのか、この辞書で勉強したという小室さんにお聞きしたいですよね。
それから、この版から、日本語に精通していたダッチャーさん(David P. Dutcher)とボイドさん(Stephen A. C. Boyd)が編集委員に加わって、用例を作成してくれたんですね。ところが、ダッチャーさんの字が読みづらくて(笑)、小稲先生のご指示で私が用例に目を通して訳をつける仕事をしました。編集部の逸見一好さんや長井寛三さんから、小稲先生が良い訳がついてると評価してくれているという話が入ってきて嬉しかったですね。
また、「『新英和中辞典』(第5版)の使い方」の冊子を書くように言われて、「辞書の引き方」と「この辞書の特色と効果的な使い方」と2部構成で書きました。
『英和中』は、4版から5版にかけて大きく変わり、6版はその延長線上にあるのに対して7版は4版へと回帰したような印象があります。6版までは吉川先生のお名前がありますが、7版にはありません。土肥一夫さん(元東京都市大学教授)、浦田和幸さん(東京外国語大学名誉教授)にきちんとバトンが渡せたらよかったのですが、出版社も厳しい状況に置かれていると思われるので、8版があるのかどうかわからないですよね。
-
辞書の仕事は楽しかったですか。

-
辞書の仕事をしていたときには、楽しいというか、ひとつの仕事だと思ってやっていた面があります。子どもが父の日に、お父さんはいつも書斎で椅子の音を立てながら仕事をしている、というような作文を書いていたということなので、若い頃はかなりの時間を辞書執筆に費やしていたような気がします。授業をするうえでも辞書の仕事からの気づきがありましたし、またその逆もしかりです。
ただ、今になって振り返ってみると面白かったのだと思います。最近、夜眠れないときに、45分の Sleep Timer をかけてイギリスの LBC (Leading Britain’s Conversation) を聞くことがよくあります。ぼんやり聞いていると眠りにつけることもあるのです。でも、表現がひょいっと耳に飛び込んでくると気になってしまうことがあります。そういう場合には辞書で確認などして返って目が覚めてしまいます。この前は、business continuation というのが気になって、continuation を引くと、continuation in ~ とか continuation of ~ の用例は出てくるけれども、複合名詞の例はないな、とか。また、『コンパスローズ英和辞典』(2018)は generosity を見出し語として立てていないことに気付いたり。curious⇨curiosity からgenerous⇨generosityを推量させるのもいいかもしれませんが。vast majority of…が耳に残ったときには、後で調べて『新英和中辞典』(5版)では「The great majority approved the policy. 大多数の人はその政策に賛同した(*用法 majority を強調する形容詞は great)」と記述されていますが第7版では「The great [vast] majority approved the policy. 実に大多数の人がその政策に賛同した」 のように変更されて、用法の説明は削除されています。unwavering commitment, unduly lenient, rampant corporate greed なども最近耳に残ったフレーズです。目に入ってきたもので忘れないのは Talk of the devil と話していたら教会から牧師さんが出てくる漫画です。このTalk [Speak] of the devil をいくつかの辞書で読んでみると記述内容が少しずつ変わっていて面白いです。辞書は改訂によって記述方針が変わりますが、言葉の実態を映し出そうとしているのですね。こういう些細なことを挙げればきりがないのですが、このようなことに何か面白味を感じられれば辞書の仕事は楽しくなりますね。そうでない時には吉川先生ならショパンを聞き、竹林先生なら(多分)モーツアルトを聞き、東先生ならマーラーの1番「巨人」などを聞いたのかも知れません。頭を、頭脳を休めるために。あるいは仕事をはかどらせるために。私は Classic FM を流しました。
-
辞書執筆者にとって大切なことは何でしょうか。

-
辞書の執筆者は当然ながら執筆要領に従って担当の項目を執筆していくわけですが、普段から絶えず英語に接していることが大事だと思います。その努力の中で執筆に必要な何かが見えてくるのです。それに何より英語感覚を磨くことができますからね。英文と音声と両方ですね。また、日本語に関しては、ことばの微妙な違いに敏感でなければならないと思います。ある人を「強い」と形容するのか「きつい」と形容するのか。「触わる」のか「触れる」のか。語義や用例の執筆も編者や執筆者の言語観が反映されるであろうと考えます。英語であろうと日本語であろうと、言葉の持つ意味をできるだけ正確に記述するとともに、その背後にある微妙な意味の違い、意味合いなども伝えられるような工夫が必要かも知れません。これからはますますコーパスが重要になってくると思われるので、そのコーパスを余すところなく読み取り使えるだけの英語力がやはり求められると思います。最後に、辞書は編者、執筆者だけで作るものではなく、編集部との合作であることも肝に銘じておくべきですね。
-
05.-
インタビューを終えて

